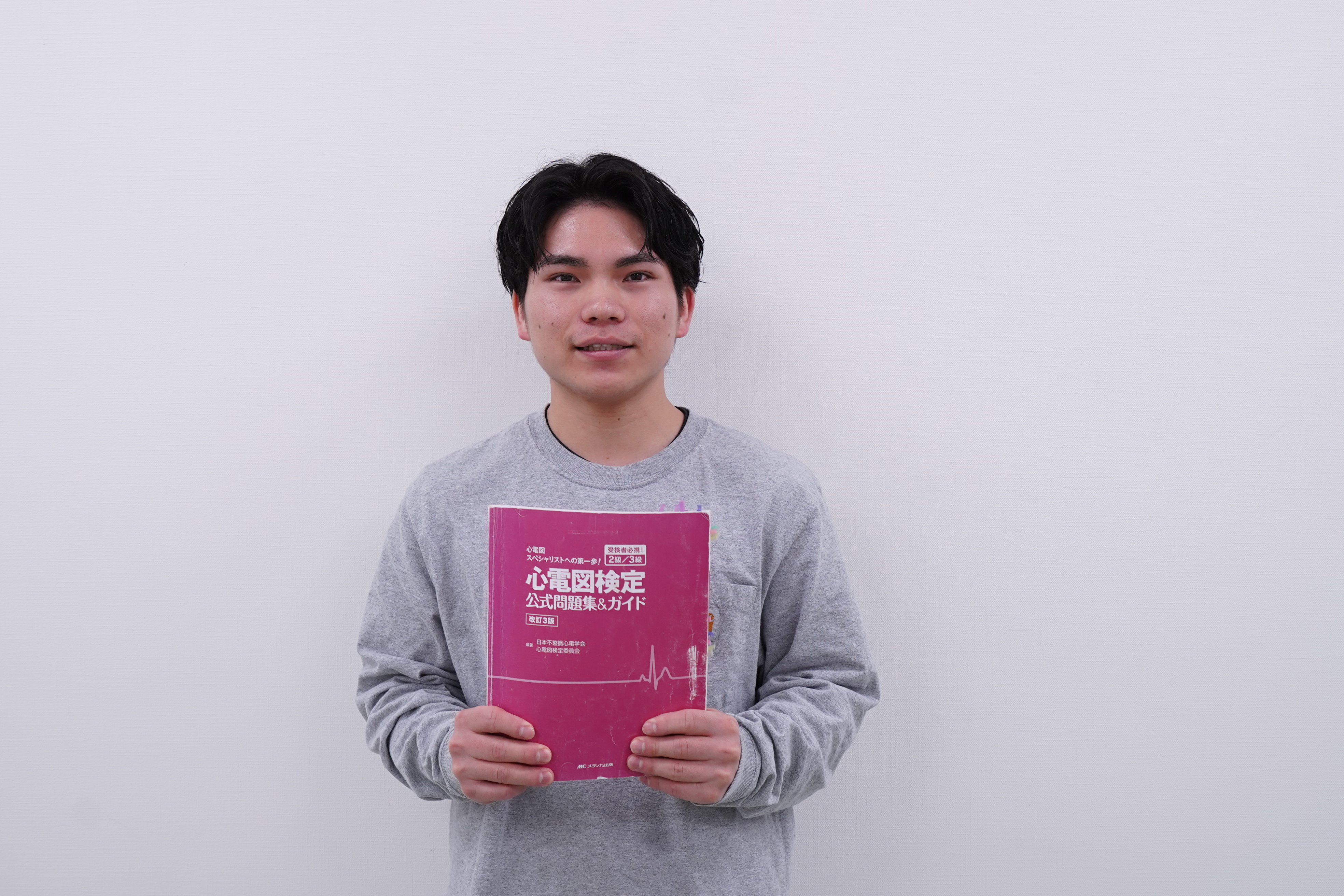NEWSお知らせ
[2025.03.18]
2024年12月に行われた第10回心電図検定試験で、本学臨床工学科4年池田 龍之慎さんが見事1級に合格しました。
心電図検定は、心電図を正確に判読する能力を測る検定試験です。最も難易度が高い1級では、心電図に対するより細かい知識や疾患との関連が問われ、臨床現場で活躍する医師でも合格するのが難しいといわれています。
今回快挙を達成された池田さんに広報課でインタビューを実施しました!
心電図検定にチャレンジしたきっかけは?
臨床工学科に入学後何か医療系の資格を取ってみようと思い、先生に勧められたのがきっかけで2年生の時に心電図検定3級を取得しました。勉強をはじめたことで心電図のおもしろさに目覚め、1年後には2級を受けて合格しました。
1級の難易度の高さは聞いていましたが、4年前期に行った臨床実習で心電図の知識が役立つ機会が多く、現場での必要性を感じたため、受験することを決めました。
1級に合格するまでの勉強時間は?
4年生の3月に受験する臨床工学技士の国家試験に向けた勉強を最優先する必要があったため、心電図検定の勉強は11月終わりから12月初めの1~2週間で1日5時間程度集中的に行いました。2・3級にすでに合格していたので勉強法を確立しており、それぞれの波形になる理由と疾患の基礎知識が頭に入っていたため短期間で合格することができました。
4年生の3月に受験する臨床工学技士の国家試験に向けた勉強を最優先する必要があったため、心電図検定の勉強は11月終わりから12月初めの1~2週間で1日5時間程度集中的に行いました。2・3級にすでに合格していたので勉強法を確立しており、それぞれの波形になる理由と疾患の基礎知識が頭に入っていたため短期間で合格することができました。
心電図検定の合格で得られるメリットは?
1級受験前に行った就職活動では心電図検定2級を持っていることについて面接で聞かれるなど、資格が役立ったと感じました。また実習では心電図の知識が現場での実践と結びつく機会が多かったため、後輩たちには4年前期の臨床実習に行く前に心電図の勉強をしておくことをおすすめします。
就職後も臨床工学技士はアブレーション(心臓に血管を通じてカテーテルという管を挿入し不整脈の原因である部分を焼き切る治療)やPCI(狭心症や心筋梗塞の患者さんに行うカテーテルを挿入して冠動脈を広げる治療)、ペースメーカー業務など心電図の知識が役立つ業務が多いため、臨床でもこれまでの学びを役立てていきたいです。
今後の目標は?
4月からは大学病院に就職します。どこに配属されたとしてもこれまで培ってきた学びへの探求心を活かし、業務を突き詰めていきたいです。
【臨床工学科 稲田 慎教授からのコメント】
目標に向かってコツコツと努力を重ね、心電図検定1級合格を勝ち取られたこと、たいへん嬉しく思います。
その意欲は、臨床工学技士となってからも活かされるものと思います。
4月からは臨床工学技士として、患者さんのために、病院スタッフのために、大いに活躍されることを期待しています。