診療放射線学科 カリキュラム/学生の声 CURRICULUM AND FACILITIES
カリキュラム紹介
専門的なスキルと医療人としてのマインドを育成するカリキュラム
医学と放射線の基礎を学び、医療人としての土台を構築
| 人間や社会を 深く理解する科目 (教養科目) |
基礎ゼミナール/物理学/生物学/化学/情報処理/統計学/心理学/生命倫理学/社会福祉学/日本国憲法/英語Ⅰ(初級)/英語Ⅱ(中級) |
|---|---|
| 全学科の学生が 共通して学ぶ科目 (学部共通科目) |
MBS〈Morinomiya Basic Seminar〉/チーム医療見学実習/基礎体育/健康科学(スポーツ社会学を含む) |
| 人体構造や病気の 成り立ちを学ぶ科目 (専門基礎科目) |
数学/数学演習/物理学演習/生物学演習/化学演習/医療技術入門/BLSテクニカル演習/循環器診断技術演習/医学概論/公衆衛生学/解剖学演習/人体の構造Ⅰ/人体の構造Ⅱ/人体の機能Ⅰ/人体の機能Ⅱ/生化学/病理学/医用工学演習/医用工学/ICT序論/医療統計学/放射化学/放射線生物学/放射線化学・生物学演習/放射線物理学序論/放射線物理学/放射線計測学Ⅰ/放射線概論 |
| 診療放射線を 専門的に学ぶ科目 (専門科目) |
医療画像情報学序論 |
| より高度な 専門領域を学ぶ科目 (専門科目) |
- |
| 先進科学技術を学び、 研究に取り組む科目 (研究分野) |
- |
放射線医療に関する専門領域を学修
| 人間や社会を 深く理解する科目 (教養科目) |
哲学/東洋史概説/英会話/医学英語/基礎英語演習/応用英語演習 |
|---|---|
| 全学科の学生が 共通して学ぶ科目 (学部共通科目) |
医療コミュニケーション/チーム医療論/健康管理学Ⅰ/健康管理学Ⅱ/栄養学/身体運動科学 |
| 人体構造や病気の 成り立ちを学ぶ科目 (専門基礎科目) |
臨床医学Ⅰ/臨床医学Ⅱ/薬理学/看護学概論/放射線計測学Ⅱ/専門基礎科目実験 |
| 診療放射線を 専門的に学ぶ科目 |
X線撮影技術学Ⅰ/X線撮影技術学Ⅱ/X線機器工学/放射線撮影技術学(US・眼底)/X線CT技術学(機器・検査)/放射線技術学実習Ⅰ(撮影系)/画像解剖学Ⅰ(単純X線画像)/画像解剖学Ⅱ(造影X線画像)/核医学検査技術学Ⅰ/核医学機器工学/放射線治療技術学Ⅰ/放射線治療機器工学/画像工学/医療画像情報学/放射線安全管理学/放射線技術学実習Ⅱ(安全管理系) |
| より高度な 専門領域を学ぶ科目 |
- |
| 先進科学技術を学び、 研究に取り組む科目 (研究分野) |
- |
実技・実習により、技師としての臨床力を高める
| 人間や社会を 深く理解する科目 (教養科目) |
西洋史概説 |
|---|---|
| 全学科の学生が 共通して学ぶ科目 (学部共通科目) |
IPW論/東洋医療概論/統合医療概論 |
| 人体構造や病気の 成り立ちを学ぶ科目 (専門基礎科目) |
臨床医学Ⅲ |
| 診療放射線を 専門的に学ぶ科目 |
MRI撮像技術学Ⅰ(機器・検査)/MRI撮像技術学Ⅱ(検査)/放射線技術学実習Ⅲ(検査系)/画像解剖学Ⅲ(各種断層画像)/核医学検査技術学Ⅱ/放射線技術学実習Ⅳ(核医学系)/放射線治療技術学Ⅱ/放射線腫瘍学/放射線技術学実習Ⅴ(治療系)/医療情報学/放射線技術学実習Ⅵ(画像解析系)/放射線関係法規/医療安全管理学/臨床画像学演習/臨床画像解析学/臨床実習Ⅰ/臨床実習Ⅱ/臨床実習Ⅲ/臨床実習ゼミナールⅠ/臨床実習ゼミナールⅡ |
| より高度な 専門領域を学ぶ科目 |
- |
| 先進科学技術を学び、 研究に取り組む科目 (研究分野) |
研究法入門/卒業研究Ⅰ |
より高度な放射線医学を学ぶ
| 人間や社会を 深く理解する科目 (教養科目) |
- |
|---|---|
| 全学科の学生が 共通して学ぶ科目 (学部共通科目) |
|
| 人体構造や病気の 成り立ちを学ぶ科目 (専門基礎科目) |
|
| 診療放射線を 専門的に学ぶ科目 |
|
| より高度な 専門領域を学ぶ科目 |
診療放射線技術総論/診療放射線学総合演習Ⅰ/診療放射線学総合演習Ⅱ |
| 先進科学技術を学び、 研究に取り組む科目 (研究分野) |
先進医療技術Ⅰ/先進医療技術Ⅱ/卒業研究Ⅱ |
黄文字 必修科目
黄太字はチーム医療カリキュラム
(上記は2025年度入学生のカリキュラムであるため、科目名等は変更になる場合があります)
診療放射線学科
専任教員による授業
95.4%
※専門教育(必修科目)における割合(2024年度)
PICK UP!
授業ピックアップ
X線撮影技術学Ⅰ(2年次)
X線を用いた撮影法や撮影装置の使用法を学び、撮影技術を身につけます。X線撮影に必要な画像解剖とポジショニングの関係、写真の見方、評価基準、被曝の低減と防護の方法など、基礎的な能力を高めることを目標とします。

臨床画像学演習(3年次)
脊柱、上肢、下肢などの骨撮影や、胸・腹部撮影を中心とする単純X線画像、およびX線CT、MRIの断層画像を分析します。どのような陰影がどういった疾患につながるのかを体系的に学びます。

STUDENT'S VOICE [在学生ピックアップ]

経験豊富な先生方の理解しやすい授業で、
1年次から専門的な知識が身につけられます。
塩見 公希 さん
診療放射線学科3年[大阪府・金光大阪高等学校出身]
早期から専門的な学びがあり臨床を感じられる!
1年次の早い段階から、身体や疾病に関する基礎的な学修に加えて「放射線生物学」「放射線物理学」といった専門的な授業もあり、高いモチベーションで学びに取り組んでいます。先生は臨床経験が豊富で、学生のことを気にかけてくれる方が多いのも、森ノ宮医療大学の魅力の一つ。ただ知識を教わるだけでなく、医療現場での実体験を交えて話してもらえるので想像しやすく、臨場感をもって深く理解できているように思います。覚えることが多いですが、学内には静かで集中できるスペースもあるので、自学自習にも取り組んで頑張っています。
一人ひとりの力量が画像に出る、奥深い世界が面白い。
今夢中になっているのは「X線撮影技術学」。いわゆるレントゲンの撮影技術を学ぶ授業。患者さんの疾患や傷がいの状況に合わせて、どのような姿勢で撮影すればよいか、臨床の現場に直結する知識を身につけます。誰が撮影しても同じというものではなく、一人ひとりの技術次第で、撮れる画像はさまざま。医師に指名されて撮影する技師もいるほどだと先生に聞いたとき、とても奥深い世界なのだと感じ、一層興味が高まりました。現場で頼られる技師をめざして、これからも頑張ります。
時間割モデル例
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 救急災害医学 | CT・MRI機器工学 | 病理学 | ||
| 2 | 内科学Ⅱ | X線撮影技術学Ⅱ | |||
| 3 | 撮影技術学・ 機器工学実験Ⅰ |
核医学検査技術学Ⅱ | |||
| 4 | 放射線治療技術学Ⅱ | ||||
| 5 | 医療情報学 | チーム医療論 |
2024年度後期時間割(10月〜3月)(2年生)

チーム医療を学ぶなら森ノ宮!
医療現場さながらのリアルな
実習室も魅力です。
鈴木 陽花 さん
診療放射線学科4年[大阪府・夕陽丘高等学校出身]
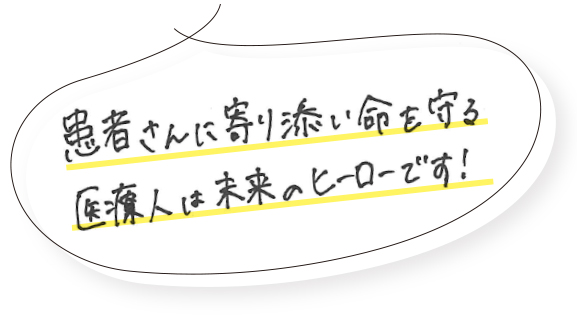
「チーム医療」に特化したカリキュラムが魅力!
森ノ宮医療大学を選んだ理由は何と言っても「チーム医療」を学べる環境にあると思ったから。診療放射線学科以外にも多くの学科があって、そのすべてが医療系の学科なのは魅力でした。多職種について学べる科目の中で、特に「チーム医療論」という授業は印象に残っています。他の学科の先生が教えに来てくれる授業で、例えば看護師と診療放射線技師の関りを学んだり、鍼灸治療という東洋医学的な視点を学んだり…、多職種への理解を深められました。授業以外のキャンパスライフでも色んな学科の友達ができるので、私には理想の環境です。
「まるで病院」なキャンパス。
実習室の扉を開けると、中にはさまざまな検査室が並ぶ病院のような造りが広がっています。そこにはいわゆるレントゲン撮影をする一般撮影装置から、磁力で体内を撮影するMRIまで、さまざまな機器が。その中でも私が興味を持っているのはX線で体内を撮影するCTスキャン。何度も触れていろいろと動かして練習できるので、気に入っています。細部まで病院内部が再現されているので、医療現場を想定した学びができるのがおすすめポイントです!
【診療放射線学科】授業潜入レポート「医療人のとびら」
カリキュラム・ポリシー :[ 教育内容 ]教育課程編成・実施の方針
診療放射線学科ではディプロマ・ポリシーに掲げるチーム医療における使命を理解し、診療放射線技師としての職責を自覚し、実践できる人材に成長できるよう知識や技術等の修得をめざして教育課程を編成しています。学位取得に向けた教育内容、教育方法、学修成果の評価方法を以下のように定めます。
教育内容
- ①1、2年次には教養科目、共通科目ならびに専門知識の基礎を修得し、診療放射線技師の礎となる知識、技術、人間力の習得をめざします。
- ②3、4年次には1、2年次に学修した知識を基に臨床実習において、臨床現場で活用できる知識、技術、さらにはチーム医療における自らの役割について学修し、専門職医療人としての確固たる知識・技術を身に付けるために、実践的な実習を中心に演習や講義に取り組みます。
教育方法
- ①医療知識、教養知識を修得するための講義科目を配置します。
- ②臨床実習において活用できる技術、知識の修得を目標とした実習科目を配置します。
- ③他職種連携教育(IPE)を積極的に導入し、チームで模索・討議し、協調性をもって解決策を検討するチーム医療実践のための演習科目を配置します。
- ④予習、復習などをシラバスに記載し、学修すべきポイントを明確にすることで、積極的に課題を見出し自ら問題解決に取り組む主体的な学修を促す手法で教育を行います。
学修成果の評価方法
- ①科目ごとに学修到達目標を明確にし、目標到達度に応じて学修成果の評価を行います。
- ②ルーブリック等を積極的に活用し、評価基準を教員・学生ともに共有し、評価の透明性・公平性が確保された手法で学修成果の評価を行います。
