- 研究領域
- 中枢神経系における準備状態と立位姿勢制御の関係
- 経歴
- 平成12年5月 理学療法士免許取得
- 平成18年6月 博士(医学)
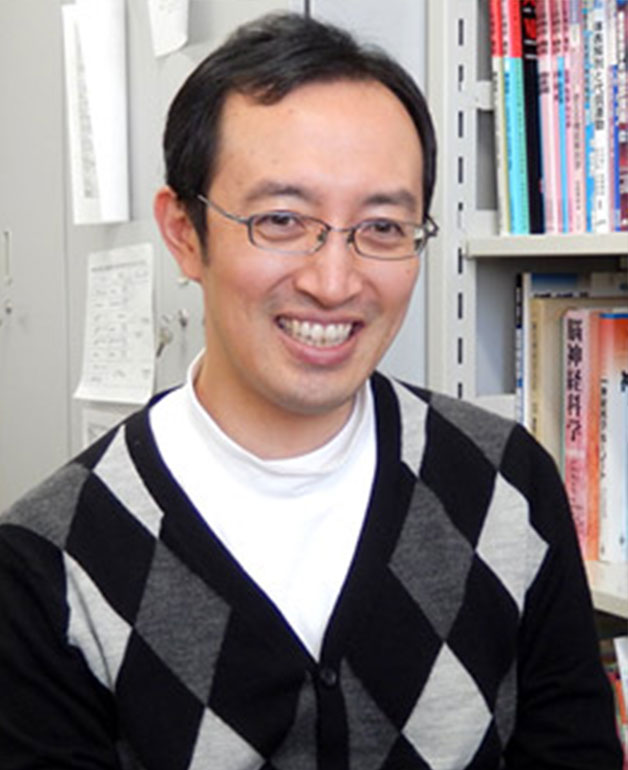
理学療法の中でも、どんな研究をしているのですか?
姿勢の調節について研究しています。姿勢は色々な動作の基本になるものであり、姿勢の調節を改善することは、理学療法士にとって非常に重要な仕事の一つといえます。
具体的には、何を調べているのですか?
脳波や脳表面の血液の流れを調べ、それと、姿勢を調節する筋肉の活動や身体の揺れがどのように関係しているかを調べています。人が刺激に対して注意を向けたり、多くの情報の中から必要なものを見つけたりする「注意機能」が低下すると、自分の姿勢の傾きやゆがみなどを正しく認識できなくなることが知られていますが、「注意機能」に関わる脳活動の記録は少ないので、それと姿勢に対する知覚がどう関係しているかについて研究しています。
それらの研究は、どんなかたちで臨床に応用できますか?
脳卒中などの患者さんで、姿勢の調節がうまくできない方にどんなリハビリや治療が効果的なのかを検証する際に応用できると思います。実際に高齢者の方々に被験者になってもらい、姿勢の調節と脳活動の関係にどんな特徴があるかを調べたりしています。
先生は、なぜ医療の道に進んだのですか?
中学時代は、弁護士や裁判官を目指していました。英語が得意科目だったので、大学では語学を学びたいと考えていた時期もありました。ところが、高校時代にラグビー部の練習でひざを骨折したとき、整形外科医がひざの状態を非常にわかりやすく、理路整然と説明してくれたことに感銘を受けて「あ、こんな職業いいな」と思ったのです。それを機に医療の仕事に興味を持つようになり、高校の先生にすすめられて理学療法士の道を選びました。
「理学療法士」の魅力とは何だと思いますか?
生活するには、やはり何らかの動作ができないと困ります。手足が動かせない人でも、口や目で意思を伝えられることがあります。そういう、生活の重要な部分を占める動きというものを改善していけるところに、理学療法士の存在価値があるのではないでしょうか。疾患を治すのは医師ですが、理学療法士は生活の質を向上させるため、運動機能を改善するスペシャリストであり、看護師など他の医療従事者からも頼られる存在です。
森ノ宮医療大学の学生について、どう思いますか?
自分の学生時代と比べると、授業時間外も実技室で練習したり学生ホールで勉強したり、非常にまじめですね。開学7年目で、自主的に勉強するという伝統ができてきたのかなと思います。(学外での学生の様子は)フェイスブックで知る程度ですが、普段も色々楽しんでるみたいで、ちょうどいいのではないでしょうか。
(平成25年12月3日)
